【八王子】相続に向けて公正証書遺言を用意するメリットとは?
【八王子】相続をスムーズに済ませるためには遺言の用意が大切
相続では、トラブルが生じることがあります。リスクを抑え、スムーズな相続を済ませるためにも、遺言は事前に用意しておきましょう。
こちらでは、八王子の弁護士が公正証書遺言のメリットと手続き、遺言書作成時の記載事項と注意点、遺言書作成にかかる具体的な費用相場についてご紹介いたします。
公正証書遺言のメリットと手続き
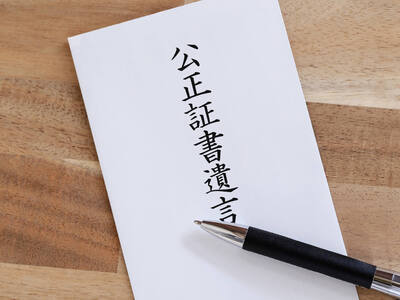
公正証書遺言のメリット
・無効となるリスクが低い
公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成を担当します。公証人は、裁判官や検事を経験した準国家公務員であり、法的な知識を豊富に備えています。そのため、遺言書が形式上の不備などで無効となる可能性が低いのが特徴です。
・信用度が高い
公正証書遺言の作成には、2人の証人が立ち会う必要があります。これにより、遺言内容の信頼性が確保されます。また、遺言作成時には、遺言者自身が実印と印鑑登録証明書を提出するか、もしくは運転免許証などの身分証明書を提示し、厳格な本人確認を受けなければなりません。このプロセスによって、遺言が遺言者本人の意思によるものであることが確認され、さらなる信用性が担保されます。
・家庭裁判所で検認をしなくてもよい
公正証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きを行う必要がありません。そのため、遺言執行が迅速に行えるというメリットがあります。
公正証書遺言を作成する流れ
・1.遺言内容のメモ作成
はじめに、ご自身で遺言内容を整理します。相続人の名前や主要な財産リスト、財産の具体的な分配方法などをメモにまとめる作業です。
・2.公証人への相談・依頼
公正証書遺言の作成を依頼する際は、電話やメールで予約しましょう。公証役場は、銀行や士業などを介さずに利用することも可能です。
・3.必要書類の提出
遺言内容を具体化したメモを公証人に提出します。その方法は、メールやファックス、郵送、または直接持参するなどさまざまです。また、遺言作成には必要な書類の提出も求められます。
・4.案の作成と修正
公証人は、提出されたメモや資料をもとに遺言公正証書の案を作成し、遺言者に提示します。その後、遺言者の確認に基づき必要な修正を行い、最終的な内容を確定します。
・5.作成日時の決定
確定した内容をもとに、公証人と遺言者で作成の日時を調整します。
・6.遺言作成当日の手続き
遺言当日、遺言者本人が証人2名の立ち会いのもとで、遺言内容を口頭で述べます。公証人は、遺言者の意思を確認し、作成した遺言公正証書を読み聞かせるか、閲覧させて内容に誤りがないか確認します。問題がなければ、遺言者と証人が署名・押印を行い、公証人も署名と職印を押捺。これにより遺言公正証書が完成します。完成後には、正本と謄本を受け取り、大切に保管します。
遺言書作成時の記載事項と注意点

遺言書作成時の記載事項
遺言書に記す内容としては、主に以下のようなものが挙げられます。
- 相続の内容(財産を誰にどのくらい相続させるのか、相続人を廃除するなど)
- 財産の内容(財産を寄付するなど)
- 身分に関わること(子どもの認知、未成年者に後見人を指定するなど)
- 遺言執行人の指定に関すること(遺言執行人を指定するなど)
これらは、法定遺言事項と呼ばれるものです。法定遺言事項とは、法的な効力がある項目を指します。遺言書は、法定遺言事項を意識しつつも正しい方法で用意しなければなりません。
遺言書作成時の注意点
遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」などの種類があります。これらのうち公証人が作成する「公正証書遺言」と、特殊な遺言の「秘密証書遺言」は除き、「自筆証書遺言」の注意点についてご紹介いたします。
・基本的に全文を自分で書く
パソコンで作成した、あるいは誰かに代筆してもらった遺言は無効となるので注意しましょう。
・作成日付を忘れずに記載する
作成日が特定できない遺言書は、無効として扱われます。作成した年月日を記しておきましょう。
・遺言者の氏名を記載し、押印する
氏名と押印が必要となるため、忘れないようにしましょう。
・法的に正しい方法で訂正する
訂正の仕方は決まっているため、我流で訂正しないようにしましょう。訂正したい箇所があれば、そこに二重線などを引き、さらに二重線の上に押印します。押印を終えたら、その横に訂正した内容を記載しましょう。
これらが済んだ後に、遺言書末尾に「〇行目〇文字削除〇文字追加」と追記します。追記は自書で行う必要があり、署名もしておきましょう。これらが手間に感じる場合は、初めから書き直すのもおすすめです。
遺言書作成にかかる具体的な費用相場
遺言書を作成する場合、「自筆証書遺言」は原則無料、「公正証書遺言」は約4万円かかります。しかし、これはご自身で対応する場合の話です。専門家にサポートを依頼した場合は、以下のような費用がかかる可能性があります。
弁護士に依頼した場合の費用
弁護士に依頼した場合、約30万円かかります。しかし、遺言の内容が複雑であったり、遺産の金額が高かったりすると、100万円を超えることもあるでしょう。
司法書士に依頼した場合の費用
司法書士に依頼した場合、約20万円かかります。一律の金額で設定しているところもあれば、遺産の金額に応じて報酬が変わる司法書士事務所もあります。
行政書士に依頼した場合の費用
行政書士に依頼した場合、約15万円かかります。一般的に他の士業よりもやや安く設定されていることが多いですが、事務所ごとに異なります。
銀行に依頼した場合の費用
銀行でも、遺言書の作成をサポートしてくれます。しかし、作成サポートを単体で行っているわけではなく、遺言信託と呼ばれるサービスの一環として対応してくれるので、その点は認識しておきましょう。遺言信託とは、遺言書の作成・保管・執行をまとめてサポートしてくれるサービスのことです。そのため、費用相場は140万円と高額になっています。
これらの金額は、あくまで目安です。サービスの内容や金額は、事務所ごとに異なります。依頼先を選ぶ際は、金額だけでなくサービスの内容もチェックしましょう。金額とサービスの内容を総合的に考えて、もっともよいと思ったところに依頼することで、満足のいくサポートが受けられます。
また、遺言書の作成だけでなく、その他の相談事項もある場合は、その点も踏まえて依頼先を決めましょう。
遺言の書き方について弁護士に相談したい方はTAM法律事務所へ
公正証書遺言のメリットと手続き、遺言書作成時の記載事項と注意点、遺言書作成にかかる具体的な費用相場についてお伝えしました。
遺言は、正しい書き方で用意しなければなりません。ご自身だけで対応が難しいと感じる場合は、相続に詳しい専門家に相談しましょう。
八王子で弁護士に遺言書について相談したいとお考えでしたら、TAM法律事務所をご利用ください。遺言書作成・執行のサポート業務を行っております。遺言がなかったことで、遺族同士の大変な争いが起きたという事案は決して少なくありません。
ご自身の死後、スムーズに相続を済ませるためには、ちゃんとした遺言書を用意することが大切です。
TAM法律事務所の弁護士は、これまで数多くの相続トラブルに対応してきた専門家です。知識はもちろん経験に基づいた遺言書作成のサポートができます。ご相談の際は、何でもお申しつけください。
八王子で遺言と相続のご相談はTAM法律事務所
| 事務所名 | TAM法律事務所 |
|---|---|
| 住所 | 〒192-0073 東京都八王子市寺町43−9 中銀八王子マンシオン 201 |
| TEL | 042-634-9450 |
| TEL | 042-634-9450 |
| URL | https://tamura-iryo.com/ |
| 受付時間 | 平日9:00〜18:00
※土日祝でも事前にご連絡いただければ、対応可能な場合もあります。 |
日常で起こるお悩みや不安は
まずは一度、TAM法律事務所へ
お気軽にご相談ください
-
 お電話でのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
042-634-9450
042-634-9450 受付時間 平日9:00~18:00 -
 メールでのお問い合わせ
メールでのお問い合わせ
お問い合わせフォーム 担当の弁護士よりご連絡いたします